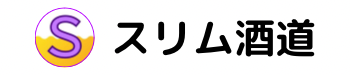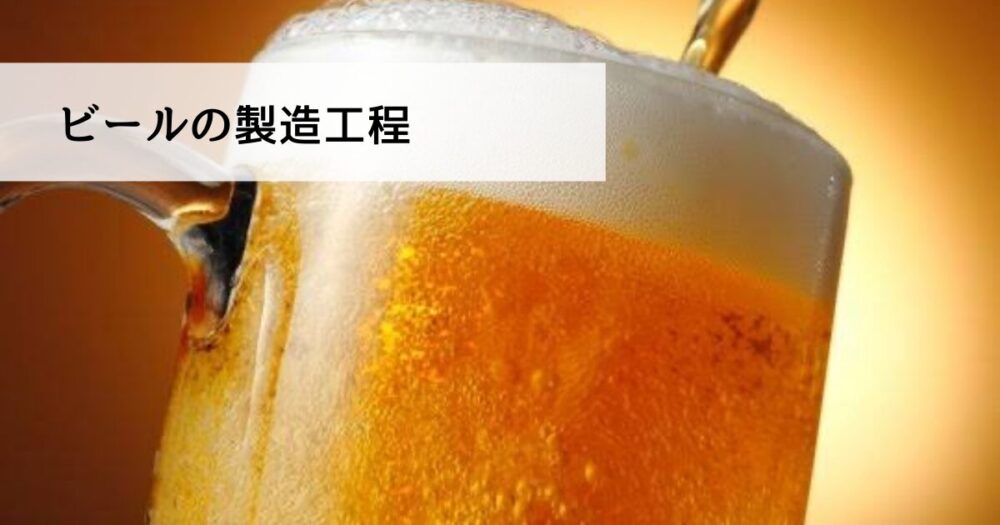ビールは世界中で愛されているお酒ですが、「どうやって作られているのか?」まで知っている人は意外と少ないかもしれません。
スーパーに並ぶ缶ビールから、クラフトビールの専門店まで、その種類は多岐にわたりますが、すべてに共通する基本的な製造工程があります。
ビールの味や香り、泡立ちの違いは、工程や使われる原料によって大きく左右されます。
本記事では、ビールの製造工程を5つの基本ステップに分けてわかりやすく解説します。
ビールの作り方|5ステップで優しく解説

- 製麦|原料を発芽させて酵素を生成
- 糖化|酵素でデンプンを糖分に分解
- 煮沸|殺菌や濃度調整など重要な工程
- 発酵|糖分をアルコールと炭酸に分解
- 熟成|短期熟成で味を安定化
1. 製麦|原料を発芽させて酵素を生成
ビールの製造工程の最初のステップは製麦です。製麦は原料の大麦を発芽させることで内部に酵素が生成されます。
【浸漬(しんせき)】
まず、原料を水に漬けて発芽させることで、内部に酵素を生成します。
【焙燥(ばいそう)】
麦芽は成長しすぎると逆に酵素が失われていくため、適切なタイミングで麦芽を乾燥させて成長を止めます。焙燥の温度によってビールの色や風味が変化します。
▼黒ビールが黒い理由は焙燥にある?▼
2. 糖化|酵素でデンプンを糖分に分解
麦芽を粉砕し、温かい仕込み水に混ぜて酵素を活性化させ、麦芽内のデンプンを糖分に分解します。
これをろ過して原料の殻などを取り除くことで、発酵に必要な糖分をたっぷり含んだ麦汁が出来上がります。
3. 煮沸|殺菌や濃度調整など重要な工程
麦汁にホップを加え、火にかけて煮立たせます。煮沸には以下の効果があります。
- 麦汁の殺菌
- ホップの苦味成分の抽出
- 余分な香気成分の揮発
- 雑味の元になる不要なたんぱく質の凝固
- 水分の蒸発による味の濃縮
ホップには苦味や香りつけの他に、殺菌効果によりビールの腐敗を防ぐ役割もあります。
4. 発酵|糖分をアルコールと炭酸に分解
前工程で生成した麦汁に酵母を加えると、酵母が糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成します。密閉した容器内で発酵させることで、炭酸ガスを逃さず発泡性を維持します。
発酵後(熟成前)の液体は若ビールと呼ばれています。
加える酵母の種類によって、ビールはエールビールとラガービールの2種類に大別されます。
▼エールビールとラガービールの違い▼

5. 熟成|短期熟成で味を安定化
若ビールは、貯酒タンクに移され、低温環境で熟成されます。
熟成中は、残存する糖分により緩やかに発酵が進みます。前工程(発酵工程)の発酵は主発酵または前発酵、熟成工程の発酵は後発酵と呼ばれています。
熟成の目的は以下の通りです。
- 主発酵だけでは、炭酸ガスの溶け込みにバラツキが出るため、後発酵により炭酸ガスを均一に溶け込ませる。
- 後発酵により残存する糖分を分解することで、甘味を減らし、ホップの苦味させる。
- 貯酒タンクの底にたんぱく質や他粒子などを沈殿させ、ビールの透明度を高める。
熟成後、ビールは容器に詰められ、市場へ出荷されます。
ウイスキーとビール、原料は同じなのに何が違う?
ここまでビールの工程を見てきましたが、似たような原料を使うウイスキーとは何が違うのでしょうか?
ウイスキーとビールはともに大麦麦芽を主原料としたお酒ですが、その出来上がりは大きく異なります。両者の違いを生む要因をご紹介します。
- ビールには蒸留工程がない:
ビールはビールはアルコールを濃縮する工程がない「醸造酒」であり、度数5〜7%と低めです。雑菌が繁殖しやすいため、ホップの添加や煮沸工程が必要になります。 - 熟成の期間:
ウイスキーが木樽による長期熟成が基本なのに対して、ビールは金属の貯酒タンクによる短期間の低温熟成が基本です。
ウイスキーと違い、ビールは後発酵を目的とした熟成のため、樽由来の香りを添加することを目的としていません。
「ホップ」の役割とは?
ホップはビールの原料として有名ですが、なぜビール製造に必須なのでしょうか?
実はホップにはビールに欠かせない重要な役割があります。
苦味や香りつけ
ホップに含まれる苦味成分「α酸」が、麦芽由来の甘さを引き締め、ビール特有の爽快感や後味のキレを生み出します。
殺菌による腐敗防止
ホップには天然の抗菌作用があり、雑菌の繁殖を抑えてビールの品質を安定させます。
ビールのアルコール度数は5〜7%程度と比較的低く、他のお酒に比べて雑菌が繁殖しやすい傾向にあります。
また、火入れ(加熱殺菌)の文化がなかった時代から飲まれており、現在でも「生ビール」として火入れせずに提供されるケースが多いため、ホップの殺菌効果やろ過・フィルター処理が品質保持において重要な役割を果たしています。
泡立ちの維持
ビールは、ビールの中に溶けている二酸化炭素がグラスに注がれた瞬間に放出されることで「泡」ができます。
しかし、ただの二酸化炭素では泡はすぐに消えてしまいます。
泡が長持ちするのは、麦芽由来のタンパク質やホップの苦味成分であるイソアルファ酸が表面に吸着し、気泡を包み込んで安定化させるからです。この構造がビールの特徴的な泡を形成しているのです。
▼ビールの泡の正体と持続のコツ▼
まとめ
ビールは、シンプルな原料から驚くほど多彩な味わいを生み出すお酒です。
その背景には、「製麦」「糖化」「煮沸」「発酵」「熟成」という5つの基本工程と、ホップや酵母といった素材の役割があります。
製造の流れを知ることで、銘柄ごとの個性や味の違いにも納得がいくはずです。ぜひ今回の内容を参考に、自分好みのビールを探してみてください。