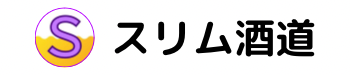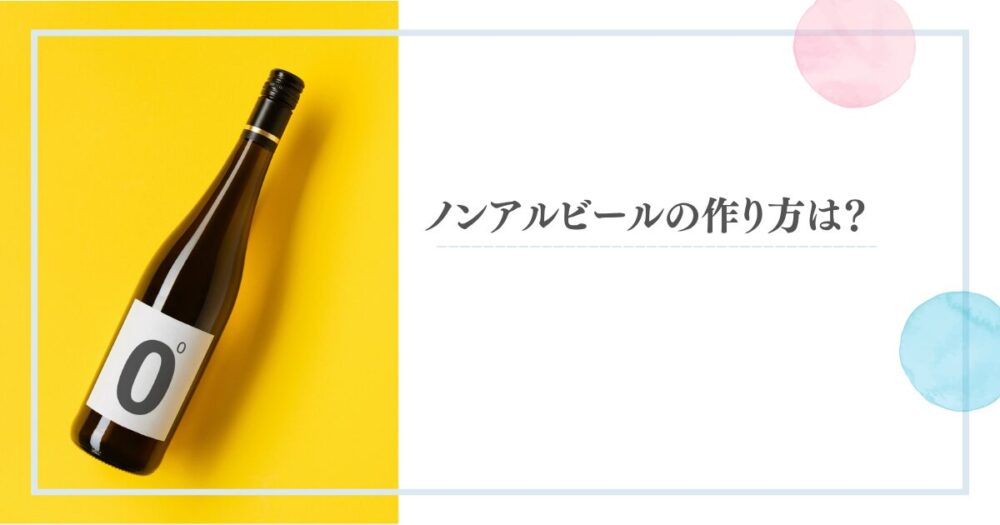ビールのような味わいなのに酔わない――ノンアルコールビールは今や定番の飲み物として定着しました。
でもふと疑問に思いませんか?
「市販のノンアルコールビールって、どうやってあんなに本物みたいな味を再現しているの?」
この記事では、工場で製造されている市販のノンアルビールの“驚くべき製造の裏側”を、分かりやすくかつ専門的に解説します。
そもそもノンアルコールビールって何?
アルコールがないビールとは?
日本では「アルコール度数1%未満」の飲料を「ノンアルコール」と分類します。
特に「0.00%」と記載されている製品は、完全にアルコールを含まないもの。つまり“ノンアルビール”とは、「見た目・味・香りはビールにそっくりだけど、酔わない飲み物」なのです。
本物のビールとの違いは?
通常のビールは麦芽を発酵させてアルコールを生成しますが、ノンアルビールでは発酵工程を“制御”または“スキップ”して、アルコールが発生しないようにするか、後からアルコールを取り除いています。
▼ビールの製造工程をわかりやすく解説▼
ノンアルコールビールの作り方|市販製品の3つの製造方法
①通常のビールからアルコールを除去する方法
最も本物に近い味わいを出せるのがこの「脱アルコール製法」です。
通常通りにビールを造り、その後「加熱」「減圧蒸留」「膜分離」などでアルコールだけを取り除きます。この方法では香りやコクを保つ工夫が求められ、製造技術の粋が集まっています。
②アルコールをほとんど出さないように発酵する方法
これは「低アルコール発酵製法」と呼ばれ、発酵時間や温度、酵母の種類を調整して、初めからアルコールを0.5%以下に抑えるようコントロールする手法です。
風味はやや軽めですが、製造コストが低く、商品化しやすいのが特徴です。
③発酵させずに味を再現する“ビール風炭酸飲料”
麦芽エキスやホップフレーバー、炭酸などを組み合わせて、ビールに似た味を再現した清涼飲料水。
これは「無発酵製法」とも呼ばれます。完全にアルコールを含まず、運転前や妊娠中でも安心して飲める設計です。
香りやコクはどうやって作ってるの?
アルコールを抜くと味も飛ぶ?
実は、ビールの“あの香り”や“深みのあるコク”の多くは、アルコールや発酵によって生まれる副産物。
アルコールを抜くことで香りも一緒に飛んでしまうため、香味成分の再添加や、ホップの濃縮エキスを用いるなどの工夫が行われています。
最新の香味再現技術
最近では「膜分離」「逆浸透」「香気成分の回収再利用」など、高度な技術により、アルコールを抜いても香りや苦味を損なわないノンアルが実現しています。
ビールマニアでも驚くほどのクオリティを持つ商品も多数登場しています。
クラフトノンアルと大手製品の違い
個性派クラフトノンアルの登場
従来は大手メーカーの製品が中心でしたが、最近ではIPA風、スモーキータイプ、柑橘フレーバーなど、多様な味を持つクラフト系ノンアルコールビールも続々登場。
これらは発酵過程にスパイスや香草を加えたり、ホップの品種を変えたりして、個性的な味を実現しています。
製造工程の違い
クラフト系は小ロット生産が多いため、手作業の比率が高く、香り付けもこだわりが見られます。
一方、大手製品は安定性と大量生産を重視し、加熱殺菌や一貫ラインでの管理によって高品質とコスト削減の両立を図っています。
代表的な市販製品とその製法の違い
完全ノンアル型(0.00%)
アサヒ「ドライゼロ」やサントリー「オールフリー」は、無発酵型やアルコール除去型をベースに、独自技術で香味を再現しています。
運転や妊娠中でも飲用可能とされ、幅広い層に人気です。
微アルコール型(0.5%未満)
海外製品に多いこのタイプは、脱アルコールや低発酵で製造され、より本格的な味わいが特徴。
「エルディンガー アルコールフリー」や「ビットブルガー ドライブ」などが該当します。
まとめ:ノンアルビールの“本物感”は技術の賜物
市販のノンアルコールビールは、「アルコールを抜く」のではなく、「どう抜いても味を落とさないか」を追求した技術の結晶です。
発酵、香味、香りの再現など、多くの職人技と研究の積み重ねによって、今の高品質なノンアルビールが生まれています。
酔わないけど、ちゃんと美味しい。そんな“不思議”の正体を知ることで、ノンアルビールがもっと面白く感じられるかもしれません。