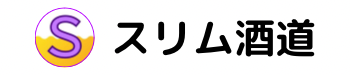アルコールとは?基本的な性質と歴史
アルコール(エタノール)の定義
アルコールの化学的な定義は「炭化水素の水素原子をヒドロキシ基で置き換えた物質の総称」であり、エタノール・メタノール・プロパノールなど様々な種類があります。
その中で飲用可能なのはエタノールだけで、他のアルコール類は毒性があり、摂取すると中毒や失明など深刻な健康被害を引き起こすことがあります。
つまり、私たちが日常的に「お酒」と呼んでいる飲料に含まれるアルコールとは、エタノール(ethanol)を指しているということです。
便宜上、当ブログでは「アルコール=エタノール」として扱います。
アルコールの生成
アルコールは、糖質を酵母によって発酵させることで生成されます。これがビールやワイン、日本酒といったお酒に含まれているアルコール成分です。
各お酒の製造方法が気になる方は、以下の記事をご覧ください。
アルコールの体への影響
吸収・代謝の仕組み
アルコールは、口から摂取後、胃と小腸から急速に吸収され、数分で血中に到達します。特に空腹時は吸収が速く、酔いが回りやすくなります。
血液に入ったアルコールは全身を巡りながら主に肝臓で代謝されます。まずアルコール脱水素酵素(ADH)によってアセトアルデヒドに変わり、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって酢酸となり、最終的には水と二酸化炭素に分解され体外へ排出されます。
日本人はこのALDHの働きが弱い人が多く、アセトアルデヒドが体内に残りやすいため、顔が赤くなる・気分が悪くなるといった「酒に弱い」体質の人が多いのが特徴です。
肝臓・脳・自律神経への作用
肝臓はアルコール代謝の中心であり、飲酒量が多いとその分負担がかかります。慢性的な過剰摂取は脂肪肝、アルコール性肝炎、肝硬変などの疾患を引き起こします。
脳に対しては、抑制系の神経を緩める作用があるため、一時的に気分が良くなったり、緊張がほぐれたりする効果があります。ただし飲みすぎると、判断力や運動機能が低下し、記憶障害や依存症のリスクも高まります。
また、アルコールは自律神経のバランスを乱すことでも知られており、寝つきは良くても睡眠の質を下げる原因にもなります。飲酒後に「眠りが浅い」「夜中に目が覚める」と感じる人が多いのはそのためです。
アルコールのカロリーと栄養成分
アルコールは1gあたり約7kcalのエネルギーを持ちます。これは脂質(9kcal/g)に次ぐ高カロリーであり、たんぱく質や炭水化物(各4kcal/g)よりもエネルギー量が大きいのが特徴です。
ただし、アルコールにはビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養素はほとんど含まれておらず、「エンプティカロリー(中身のないカロリー)」と呼ばれることもあります。
▼三大栄養素とアルコールのカロリー詳細▼
アルコールの適量と指針
「純アルコール量」とは?
お酒は、種類によってアルコール度数が異なるため、「5杯飲んだらアルコール過多」といった判断を一概にできません。
そこで指標となるのが「純アルコール量」です。純アルコール量は、お酒に含まれるアルコールの量をグラム(g)で表したもので、以下の計算式で求められます。
純アルコール量[g]
= 飲酒量[ml] × アルコール度数[%] ÷ 100 × 0.8[g/ml]
※0.8はアルコールの比重
たとえば、アルコール度数5%のビール500mlの場合、500 × 0.05 × 0.8 = 20gとなり、純アルコール量は20gです。
この「純アルコール量」が、健康指針や飲酒量の目安を考える際の基本単位となります。お酒の種類に関係なく、アルコール成分そのものを基準にすることで、ビール・ワイン・焼酎などの飲酒量を共通の土台で比較できるようになります。
厚生労働省が定める適量の目安
厚生労働省の「健康日本21」や「飲酒ガイドライン」では、1日あたりの純アルコール摂取量の上限を20g程度としています。これは「節度ある適度な飲酒」の目安であり、毎日継続して飲んでも健康を害しにくいとされるラインです。
この20gの純アルコール量は、以下のようなお酒の量に相当します。
- ビール中瓶(500ml・5%):約20g
- 日本酒1合(180ml・15%):約22g
- ワイン2杯(200ml・12%):約19g
- 焼酎グラス1杯(110ml・25%):約22g
なお、女性や高齢者は一般にアルコール代謝能力が低いため、この半分(10g程度)を上限にするのが望ましいとされています。また、週に2日以上の「休肝日」を設けることも推奨されています。
この基準は「絶対に安全」という意味ではなく、健康リスクを下げるための目安です。体質や持病、生活習慣に応じて、無理のない飲酒管理が重要です。
おわりに
アルコールは、古くから人類の文化やコミュニケーションを支えてきた嗜好品です。適量を守ればリラックス効果や社交性の向上といったメリットもありますが、過剰な摂取は健康リスクや依存症の原因となるため、注意が必要です。
本記事では、アルコールの定義や体内での代謝、カロリーや栄養的な側面、そして厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」の目安について解説しました。
重要なのは、「自分の体質・ライフスタイルに合った飲み方を知ること」です。飲酒量の目安を知り、休肝日を意識しながら、無理なく楽しめるお酒との付き合い方を見つけていきましょう。