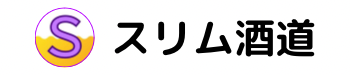一般的なワインの保存期間

ワインは「腐らないお酒」として知られていますが、実は種類や状態によって風味の持ち方には大きな違いがあります。
とくに「未開栓」と「開栓後」では、保存期間の考え方がまったく異なります。
ここでは、一般的なワインの保存期間について、未開栓ワインと開栓後ワインそれぞれの特徴をふまえて、わかりやすく解説します。
「ワインって開けたら何日もつの?」「買ったまま放置してたけど、まだ飲める?」そんな疑問にもお答えします。
未開栓ワインに消費期限はある?
ワインはpH3程度の酸性で、アルコール度数も12%ほどあります。この酸性とアルコールの力によって、未開栓であれば基本的に腐ることはありません。そのため、消費期限や賞味期限の表示義務はなく、多くのワインには実際に記載されていません。
ただし、消費期限や賞味期限がないからといって、いつまでも同じ味で楽しめるわけではありません。
ワインには「飲み頃」と呼ばれる、もっとも美味しく味わえる時期があります。
たとえば、スーパーでよく見かけるテーブルワイン(デイリーワイン)は、日常的な消費を前提に造られており、熟成を目的としていないものがほとんどです。そのため、購入時が飲み頃であり、長く置いておくと香りや風味が徐々に落ちてしまうこともあります。
開栓後のワインはいつまで飲める?種類ごとの目安
前述の通り、ワインには法律上の賞味期限は表示されないものの、風味が落ちる時期の目安は存在します
ワインは一度開けると空気と触れ合うことで酸化が進み、時間の経過とともに香りや風味が変化していきます。つまり、開栓した瞬間から、ワインの状態は少しずつ変わり始めるのです。
ただし、ここで言う変化は腐敗や劣化といった衛生的な問題ではなく、あくまで「味や香りの変化」です。ワインはアルコール度数が高く、酸性度も強いため、開栓後すぐに「腐る」ことは基本的にありません。
とはいえ、ワイン本来の魅力を味わうためには、開栓後できるだけ早く飲みきるのが理想です。保存方法にもよりますが、一般的な目安としては以下のとおりです。
- スパークリングワイン:1〜2日
- 白ワイン・ロゼワイン:2〜3日
- 赤ワイン:3〜5日
スパークリングワインは、炭酸が抜けやすいため特に短命です。開栓後すぐに炭酸由来のシュワシュワ感が失われていきます。発泡とともに酸素も混入しやすいため、酸化による味や香りの変化も早く進みます。
白ワインやロゼワインも、比較的繊細な香りや酸味が特徴であり、酸化によって風味が崩れやすいため、早めに飲みきることが推奨されます。
赤ワインは、果皮や種と一緒に発酵させて造られるため、タンニンやポリフェノールといった抗酸化成分が豊富です。これらの成分が酸化をある程度抑えてくれるため、比較的長く風味を保ちます。
味の変化は辛口ワインと甘口ワインでも違います。甘口ワインは糖分を多く含んでおり、糖の防腐効果によって比較的風味が安定しやすいです。冷蔵保存であれば1週間程度持つものもあります。
ワインの基本的な保存方法

ワインは非常に繊細な飲み物で、保存方法によって味や香りが大きく変化します。とくに温度や湿度、光、振動といった要素に注意することが大切です。
ワインの正しい保存方法について、保存場所の条件やボトルの置き方などをわかりやすく解説します。
- 温度:12〜15℃
温度が高すぎると酸化が進みやすく、香りや味が損なわれます。逆に低すぎると熟成が止まり、香りが感じにくくなります。
また、冷やしすぎると香りが立たなくなるため、ワインの風味を引き出す適温での保存が大切です。 - 湿度:60〜70%RH
湿度が低いとコルクが乾燥して隙間が空き、ボトル内部に酸素や雑菌が入りやすくなります。これにより、香りや味の劣化が進みます。
反対に湿度が高すぎると、カビの発生やワインラベルの劣化の原因になります。 - 光:直射日光や蛍光灯を避ける
紫外線はワインに含まれる成分に化学変化を引き起こし、香りや味を損ねる原因になります。蛍光灯の光も波長によっては劣化を招くため、ワインは暗所で保存するのが望ましいです。 - 振動:なるべく静かな場所
振動はワインの熟成に悪影響を与えます。瓶の中の澱(おり)が舞い上がってしまい、風味を損なうこともあります。
特に熟成させたいワインは、できるだけ静かな環境で保管するのが理想です。普段飲むワインでも、冷蔵庫のドアポケットのように揺れやすい場所は避けましょう。 - ボトルの置き方:横向き
コルク栓のワインは、ボトルを横に寝かせて保存するのが基本です。
これは、ワインがコルクに触れることで乾燥を防ぎ、密閉性を保つためです。コルクが乾くと隙間ができ、空気が入り込んで酸化や劣化の原因になります。
家庭で保存する場合は、「冷暗所(床下収納やクローゼットの奥など)」が適しています。夏場や温度が不安定な場所では、ワインセラーやワイン専用冷蔵庫の使用も検討すると安心です。
家庭で実践できるワインを長持ちさせるコツ

ワインは繊細なお酒ですが、ちょっとした工夫で美味しさを長く保つことができます。
特別な設備がなくても、家庭にある道具や場所を上手に活用するだけで、ワインの保存性はぐんとアップします。
ここでは、家庭で今すぐ実践できるワインの保管方法と、便利な保存グッズについてご紹介します。
すぐに実践できる保管方法
ワインの保存には「冷暗所」が最適で、湿度がある程度高い環境が望ましいとされています。
家庭内でおすすめの保存場所としては、床下収納やクローゼットの奥などが挙げられます。ただし、これらの場所は季節によって温度が不安定になりやすく、特に夏場はワインが劣化するリスクがあります。
そこで活用したいのが冷蔵庫の野菜室です。野菜室は冷蔵室よりやや高めの3〜8℃程度に保たれており、湿度も20〜50%程度と比較的高めです。ドアの開閉による振動が少ない点も、ワインの保存に適しています。
最近の冷蔵庫では、温度設定が細かく調整できる機種も増えており、ワイン保存に適した12〜15℃に設定するのもおすすめです。
また、野菜室にワインを保管する際は、ボトルを横に寝かせて新聞紙などで包むと、遮光性が保たれ、コルクの乾燥も防げます。手軽にできるうえ、ワインの品質を守る実用的な方法です。
ワイン保存に役立つ便利グッズ
ワインの天敵は酸化による香りと味の劣化です。ワインコルクには微細な隙間があるため、透過した酸素によってワインが徐々に劣化します。
これを防ぐために、ワインストッパーがあります。ワインストッパーはシリコンやステンレスで出来ており、コルクよりも気密性に優れ、ワインを長持ちさせてくれます。
今回は様々なワインストッパーをご紹介します。
1. シャンパン対応のワインストッパー
市販のワインストッパー(キャップ)には、さまざまな材質があります。
なかでも最も一般的なのはシリコン製です。シリコンは柔軟性がありボトル口にしっかりフィットしやすく、人体にも無害なため、広く使われています。また、価格が手頃で扱いやすいのも人気の理由です。
しかし、シリコンはガス透過性が高く、酸素が内部に入りやすいため、長期保存には不向きです。
そこでおすすめなのが、「シャンパン対応のワインストッパー」です。
このタイプのストッパーは、炭酸ガスの抜けを防ぐための密閉構造が採用されており、通常のストッパーよりも気密性が高いのが特徴です。酸素の透過も抑えられるため、スパークリングワインの保存だけでなく、長期間のワイン保存にも適しています。
2. 真空ポンプ式ワインストッパー
ワインの酸化をさらに抑えたい方におすすめなのが「真空ポンプ式ワインストッパー」です。
これはポンプ式のキャップで中の空気を抜いてボトル内部を減圧状態にすることで、酸素との接触を極力減らすアイテムです。手動ポンプで数回引くだけと使い方は簡単で、密閉状態が保たれたことを示すインジケーター付きの製品もあります。
香りの繊細なワインに効果的で、日常的にワインを飲む方にとって、コストパフォーマンスの高い便利アイテムです。
3. カーボンフィルター式ワインストッパー
「カーボンフィルター式ワインストッパー」は、活性炭(カーボン)を内蔵したストッパーで、ワインボトル内の酸化を穏やかに抑えます。
活性炭には脱臭や吸着の性質があり、ボトル内の酸素や揮発性物質を吸着することで、ワインの風味の劣化を防ぎます。真空ポンプ式のようにポンピングする手間が不要で、キャップをするだけという手軽さも魅力です。
なかでも有名なのが、プルテックス社の「アンチ・オックス」です。
「国際ソムリエくん」こと宮本隆太さんも、「真空ポンプ式よりも断然ワインの状態が良い」と絶賛しています。
ちなみに宮本さんは、国際ソムリエ協会の国際資格試験で、日本人初のゴールド認定を受けた実力派ソムリエです。