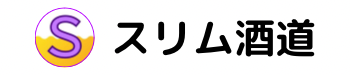カロリーとは?意味と単位
カロリー(kcal)の定義
カロリーとは、エネルギーの量を示す単位であり、正確には「1gの水の温度を1℃上げるのに必要な熱量」が1カロリー(cal)と定義されています。
しかし、日常的に使われている「カロリー」は、実際にはその1,000倍にあたる「キロカロリー(kcal)」を指していることがほとんどです。
ちなみに日本では「カロリー(kcal)」が主流ですが、欧米では「キロジュール(kJ)」というSI単位を使う国もあります。
エネルギーとの違いと使い分け
カロリーは、エネルギーの量を表す単位であり、「カロリー=エネルギーの単位」という関係にあります。
身近な例で言えば、「メートル=長さの単位」と同じような関係です。
エネルギーを表す単位にはさまざまな種類があり、私たちの生命活動や運動に必要な“エネルギー源”は「カロリー(kcal)」で表されます。
一方、機械やエンジンなどの動力源としてのエネルギーは、「ジュール(J)」や「ワット(W)」などで表されるのが一般的です。
日常会話や広告では「エネルギー控えめ」よりも「カロリー控えめ」という表現の方がよく使われますが、厳密にはカロリーはエネルギーの単位であるという点を押さえておきましょう。
消費カロリーの計算方法

私たちの1日の消費カロリーは、「基礎代謝」と「身体活動レベル(PAL)」から計算することができます。
それぞれの意味と導出方法を見ていきましょう。
基礎代謝
基礎代謝とは、何もしていなくても呼吸や体温調整、内臓の働きなどで消費されるエネルギーのことで、1日の総消費カロリーの約60〜70%を占めます。
基礎代謝の推定式はいくつかありますが、「国立健康・栄養研究所の式(Ganpuleの式)」が、健康な日本人において妥当性が高い推定式として知られています。
男性の基礎代謝[kcal] :
(0.0481×W + 0.0234×H – 0.0138×A – 0.4235) × 1000 ÷ 4.186
女性の基礎代謝[kcal]:
(0.0481×W + 0.0234×H – 0.0138×A – 0.9708) × 1000 ÷ 4.186
W:体重[kg]、H:身長[cm]、A:年齢[歳]
身体活動レベル(PAL)
身体活動レベル(PAL: Physical Activity Level)とは、1日の総消費カロリーが、基礎代謝量の何倍にあたるかを示す指標です。
計算式で表すと、次のようになります。
身体活動レベル
= 1日の総消費カロリー ÷ 基礎代謝量
身体活動レベルは、年齢や生活スタイルによって、日本医師会の推定表から求められるので、この関係を使えば、逆算により1日の総消費カロリーが算出できます。
| 日本医師会による身体活動レベルの推定表 | |||
|---|---|---|---|
| 年齢 | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ |
| 1-2 | – | 1.35 | – |
| 3-5 | – | 1.45 | – |
| 6-7 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
| 8-9 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
| 10-11 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
| 12-14 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
| 15-17 | 1.55 | 1.75 | 1.95 |
| 18-29 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 30-49 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 50-64 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 65-74 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
| 75以上 | 1.40 | 1.70 | – |
レベルⅠ :
生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
レベルⅡ :
座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む場合
レベル Ⅲ:
移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合
摂取カロリーの計算方法

食べ物や飲み物のカロリーは、その中に含まれる三大栄養素(たんぱく質・脂質・炭水化物)やアルコールの量によって決まります。
それぞれの成分が持つ「1gあたりのエネルギー量(カロリー)」は、以下の通りです。
- たんぱく質:4kcal/g
- 脂質:9kcal/g
- 炭水化物(糖質+食物繊維):4kcal/g
- アルコール(純アルコール):7kcal/g
これらの数値は、食品の栄養成分表示や計算式のベースとして広く使われており、私たちが日常的に摂取カロリーを把握したり、食事を管理するうえではこの「4・9・4・7」のルールで十分実用的です。
なお、日本食品標準成分表2020年版では、さらに細かい成分ごとのエネルギー量が掲載されていますが、一般的なカロリー計算には上記のようなアトウォーター係数(熱量換算係数)を用いるのが一般的です。
ダイエットの基本

カロリー制限と健康の関係
ダイエットの基本は、摂取カロリーよりも消費カロリーを多くすること。この差が「エネルギー赤字」となり、体脂肪が使われて体重が減少していきます。
1kgの体脂肪を減らすには約7,200kcalのエネルギー赤字が必要とされており、たとえば1日あたり500kcalのカロリー赤字を作れば、2週間ほどで1kgの脂肪を減らすことができます。
ただし、過度なカロリー制限はリスクも伴います。極端に食事量を減らすと、筋肉量の減少、代謝の低下、ホルモンバランスの乱れ、さらにはリバウンドの原因にもなりかねません。
そのため、カロリー制限は「控えめに、バランスよく」を基本に、無理のない範囲で取り組むことが健康的なダイエット成功への近道です。
ダイエットには糖質制限も重要
最近では「カロリー制限」だけでなく、「糖質制限(ローカーボ)」もダイエットの重要なアプローチとして注目されています。
糖質(炭水化物)は、血糖値を上げインスリンの分泌を促します。インスリンは脂肪の合成を促すホルモンでもあるため、糖質を過剰に摂ると脂肪が蓄積されやすくなるのです。
また、糖質を減らすと体内のグリコーゲン(糖の貯蔵分)が減り、水分も一緒に抜けるため、短期間で体重が落ちやすいという利点もあります。
ただし、糖質も身体にとって重要なエネルギー源です。極端にカットすると頭がぼーっとしたり、集中力が落ちるなどのデメリットもあるため、「緩やかな糖質制限(低糖質)」を意識すると無理なく続けやすくなります。
まとめ
- カロリーはエネルギーの単位
- 消費カロリーは「基礎代謝 × 身体活動レベル」で求められる
- 摂取カロリーは「三大栄養素とアルコール量」から計算可能
- ダイエットは「控えめなカロリー制限」と「緩やかな糖質制限」が重要