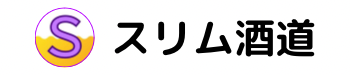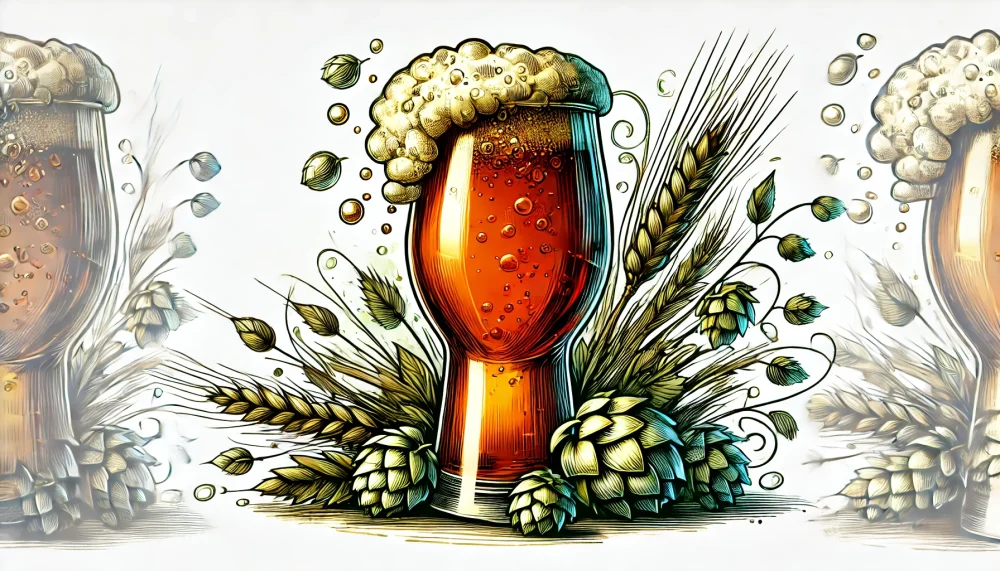そもそもプリン体とは?

プリン体とは、細胞の代謝に関与する「プリン塩基」を構成する物質であり、体内で尿酸に分解されます。
尿酸が過剰に蓄積すると、高尿酸血症や痛風の原因となるため、健康を意識する人々にとって注目されています。
プリン体はどこに含まれているのか?
プリン体は動植物の細胞に含まれており、肉・魚・内臓類、さらには発酵食品やビールなどの飲料にも存在します。
つまり、私たちは日常的にプリン体を摂取していることになります。
体内でも合成されるプリン体
実は、体内に存在するプリン体の約8割は、体内で自然に合成されたものです。
食事からの摂取は2割程度ですが、それでも過剰摂取はリスクを高める要因になります。
▼プリン体の摂取から排出まで徹底解説▼
なぜビールにプリン体が多いのか?

他のアルコール飲料と比較して、ビールは特にプリン体の含有量が高いことで知られています。その背景には、ビールの製造工程と原料の特性があります。
ビールの主原料に含まれる細胞成分
ビールは麦芽(モルト)や酵母を用いて製造されます。これらの原料は細胞密度が高く、プリン体が豊富に含まれています。特に、酵母は細胞核がある微生物であり、プリン体の供給源となるのです。
発酵工程で生まれるプリン体
ビールの製造過程では、麦汁を発酵させる際に酵母が増殖します。このとき細胞分裂が繰り返され、大量の細胞成分=プリン体が生まれます。結果として、完成したビールには高濃度のプリン体が残ることになります。
▼ビールの製造方法をわかりやすく解説▼
他のお酒とのプリン体比較

焼酎やウイスキー、ワインなどの他の酒類と比べると、ビールのプリン体含有量は明らかに高い傾向があります。これは原料や製法の違いに起因します。
蒸留酒にはほとんど含まれない
焼酎やウイスキーなどの蒸留酒は、発酵後に熱を加えて蒸留する工程があるため、プリン体を含む不揮発性成分は取り除かれます。
これにより、ほとんどプリン体を含まない「プリン体ゼロ酒」として扱われます。
▼蒸留酒の代表、ウイスキーの製造工程▼
ワインは果実が原料
ワインの原料であるぶどうは、細胞密度が麦芽ほど高くなく、酵母の残存量も比較的少ないことから、プリン体の含有量は少なめです。
▼ワインの製造工程▼
プリン体が気になる人のためのビール選び
プリン体の摂取を抑えたい方には、「プリン体ゼロ」や「プリン体オフ」と表記されたビールや発泡酒がおすすめです。
これらは酵母や麦芽の使い方に工夫が施され、プリン体含有量が大幅に削減されています。
プリン体ゼロとプリン体オフの違い
「プリン体ゼロ」は100mlあたり0.5mg未満のプリン体しか含まれていない商品に付けられる表示です。
一方で「オフ」は、通常の製品と比べて25%以上削減されていることを意味します。
飲み方にも注意を
プリン体の含有量が少なくても、過剰に飲めば尿酸値の上昇を引き起こします。1日の適量を守ることが健康維持には不可欠です。適量は中瓶1本程度(500ml前後)が目安です。
まとめ:ビールのプリン体が多いのは「原料」と「製法」が原因
ビールが他の酒よりプリン体が多い理由は、麦芽や酵母といった細胞成分の多い原料を使い、さらに発酵によって酵母が増殖する製法にあります。対照的に、蒸留酒やワインはこのような構造を持たないため、プリン体が少ないのです。
「ビール=痛風の原因」と決めつけるのではなく、飲み方や商品選びを工夫すれば、健康的に楽しむことは十分可能です。