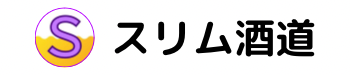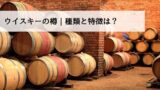ウイスキーの奥深さを知るには、まず「どう造られているのか」を理解することが大切です。
本記事では、ウイスキーがどのようにして香り豊かな一杯へと仕上がるのか、6つの基本工程に分けてわかりやすく解説します。初心者の方でも、ウイスキーの魅力がより深く感じられるようになるはずです。
ウイスキーの作り方|6ステップで優しく解説

- 製麦|原料の大麦を発芽
- 糖化|デンプンを糖分に分解
- 発酵|糖分をアルコールと炭酸に分解
- 蒸留|香りとアルコールを凝縮
- 熟成|樽の中で風味を深める
- 調合|風味やアルコール濃度を調整
1. 製麦|原料の大麦を発芽
ウイスキーは主に大麦を使います。
【浸漬(しんせき)】
まずは大麦を水に浸して発芽させることで、内部に酵素を生み出します。
【焙燥(ばいそう)】
麦芽は成長しすぎると逆に酵素が失われていくため、適切なタイミングで加熱乾燥して発芽を止めます。この時にピート(泥炭)を使うとスモーキーな香りが加わるのが特徴です。
2. 糖化|デンプンを糖分に分解
乾燥した麦芽を粉砕してお湯(仕込み水)と混ぜ、酵素の働きでデンプンを糖分に分解します。
これをろ過して原料の殻などを取り除くことで、発酵に必要な糖分をたっぷり含んだ麦汁が出来上がります
3. 発酵|糖分をアルコールと炭酸に分解
麦汁に酵母を加えると、糖分がアルコールと炭酸ガスに分解され、「もろみ」と呼ばれる発酵液ができます。アルコール度数は約7%程度です。
ここまでの工程はビール製造とほぼ共通しています。
4. 蒸留|香りとアルコールを凝縮
発酵によってできたもろみを、蒸留器で加熱します。
沸点の違い(水は100℃、アルコールは78.4℃)を利用して、アルコールや香気成分が凝縮した、「ニューポッド」と呼ばれる液体を抽出します。
蒸留器は連続式蒸留器と単式蒸留器に大別されます。
連続式蒸留器は単式蒸留器よりも効率的にアルコール度数を上げることができ、それゆえ大量生産に向いています。
一方、一気に蒸留するため、アルコール以外の成分が残りづらいです。アルコール度数も高くなるため、後工程で多くの水を加えなくてはならず、味に深みがなくなります。
5. 熟成|樽の中で風味を深める
蒸留したニューポットを木樽に詰めて長期間熟成させることで、まろやかな風味や色が加わります。
熟成期間が長いほど、樽由来のバニラ香やウッディなニュアンスが強まります。
▼樽の種類による風味の違いはこちら▼
6. 調合|風味やアルコール濃度を調整
最後は熟成された原酒を複数ブレンドし、味や香りを整えます。水を加えてアルコール度数を調整することもあります。
この工程によって、ウイスキーの個性が決定づけられます。
調合の組み合わせによって、「モルト」「グレーン」「ブレンデッド」など、さまざまなウイスキーの種類が生まれます。
▼ウイスキーの種類をわかりやすく解説▼
ウイスキーとビール、原料は同じなのに何が違う?
ウイスキーとビールはともに大麦麦芽を主原料としており、「発酵」までの工程はほぼ共通です。
大きな違いは、ウイスキーは蒸留により香味やアルコールを凝縮する「蒸留酒」なのに対して、ビールは蒸留を行わない「醸造酒」であることです。
この違いが、ビールとの風味や度数の差を生み出しています。
- アルコールの生成方法と濃度:
ビールは発酵のみ(4〜7%)
ウイスキーは発酵+蒸留(40〜43%) - 熟成の有無:
ビールは熟成なし(または短期間)
ウイスキーは長期熟成が基本 - 香味の付け方:
ビールは麦芽+ホップ
ウイスキーは麦芽+木樽
ウイスキーの場合、蒸留により炭酸が除去されるので、ビールのような発泡性はありません。このように、同じ麦芽でも製法が異なれば、まったく別のお酒に生まれ変わるのです。
ウイスキーと焼酎、同じ蒸留酒なのに何が違う?
ウイスキーと焼酎はどちらも蒸留酒ですが、原料や製造方法、味わいに明確な違いがあります。
- 原料:
ウイスキーは麦芽や穀物
焼酎は米・芋・麦など地域により様々 - 蒸留法とアルコール濃度:
ウイスキーは単式 or 連続式(40〜43%)
焼酎は単式(20〜25%) - 熟成:
ウイスキーは数年〜数十年の熟成
焼酎は熟成しないか短期間
ウイスキーは長時間木樽で熟成させるため、樽材の成分が溶け出し、琥珀色になります。
まとめ|製造工程を知ると、ウイスキーがもっと面白い
ウイスキーの風味は、素材や技術だけでなく、6つの工程それぞれが関与して生み出されています。
製法を知れば、ラベルの表記や産地の違いにも興味がわき、自分好みの一杯に出会いやすくなるでしょう。